
全長 350[mm]
全幅 250[mm]
全高 550[mm]
重量 3500[g]
腕機構 シールドアーム 380モータ×4 最終ギア比150:1
脚機構 120度位相スライダーヘッケン機構380モータ×4 最終ギヤ比21:1
大会参加結果
ROBOT WARS 2015 in 未来館
不戦敗
第22回かわさきロボット競技大会
予選トーナメント
第一試合 空飛ぶ亀 勝
第二試合 interface 敗
予選トーナメント敗者復活戦
第一試合 OESpear・Triaina 敗
ロボット名の由来
製作者の名前から
χが全角、他が半角で非常に汚いので何とかしたいです。
脚
380を4個使用。減速比は20:1。脚はスライダヘッケンリンク機構を利用。
脚が早すぎて扱えないのはご愛嬌。いつかきっとこの速度に慣れる日が来るはず….
前脚にサスペンションを導入。コレにより山に侵入した際の不規則な方向転換が無く、思ったように動く機体になりました。速すぎるけど 空飛びました。
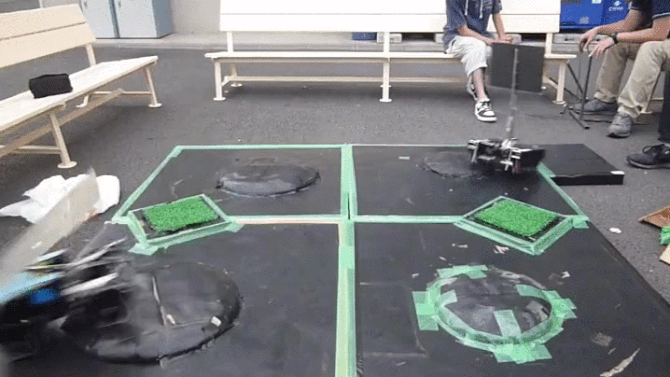
脚周りの減速系にはギヤボックスを使わずに市販ギヤを使用しました。
しかし、動力伝達のキーのキー溝が20試合目あたりで削れてキーが取れてしまった。もともとキーはしっかり圧入出来ていたので高回転数のところで使用してしまった点とギヤの厚さが小さかった点が問題だと思われる。
そのため、KHK杯で市販ギヤを追加工したものを使用。NCによる追加工でも中心がずれるかも知れないので穴をいじるのは辞めたほうが良いです。 NCで追加工してピンで次の段に繋いでいたが、曲がってしまった。

始めはクランク軸を2点締結していたが、すぐにネジが緩んでしまった。
KHK杯ではクランク軸をNCと旋盤で自作した。ねじ山には廣杉のインサートナットを使用。入れるためには特殊工具が必要なので注意。

腕
去年から続けていたアームギヤボックスの完成形が見えてきた(気がします)
初段は協育歯車のS50S 110*0508を使用。
軸受けは最初全ての段にボールベアリングを用いたが、3段目(ギヤ比が55になる段)から玉が潰れてしまったため、初段はボールベアリング、最終段はオイレスベアリング、それ以外の段はニードルベアリングにしました。アームも速すぎて扱えないのでスペース的な余裕があればポテンションメーター導入などしたいです。
始めは腕もポリカーボネートのフレームだったがアームのトルクで歪み、効率低下したのでアルミに変更。
聞かれた事のまとめ
1. ポリカーボネートのフレームってどうよ?
利点欠点をまとめると。
利点
① 色がつけやすく美しい。
② 切削の時間が短い。(T3でエグい肉抜きをしたアルミとT5でエグいポケット加工肉抜きをしたもので比べても速かった)
③ 壊れる時ひずみが残る前に割れるため、脚への影響が少ない(脳内)
④ 適当に嵌め合いをとってもいい感じにベアリングが入る
⑤ 板厚を大きく出来るのでネジが入る長さが長くなり、適当に組んでもねじ山が舐め難い。
⑥ 板が柔らかいため座金が無くても締め付けが強く、緩み辛い(ポリカーボネートに対応したねじロックもあるのでもしもの時はそれで)
欠点
① ポリカのバネ性が進行方向に垂直な方向に効いてしまう(板をスペーサで挟んでいるのが原因 うまくバネ性を活かせればイイネ)
② その柔らかさ故に軸受けが歪み効率低下に繋がる(アームのギヤトレインには良くない)
③ 専用の物意外の接着剤をつけると割れる。
④ 比強度はアルミが上 ここ重要
加工時間が短いので修羅場率が高いうちではポリカ導入が良いかもしれません。
ただ適材適所なので、実際に使っている人に相談しましょう
2. リフェバッテリってどうよ
今すぐ買ってきた方がいいよ。と思うくらい良い。そもそも何時も使っているニッスイだときちんと必要な電流量を吐けて無いので絶対にリフェにしたほうがいいです。注意点は
① 電圧が落ちるときは一気に落ちるのでバンバン追い充電しましょう(ニッスイは追い充電すると良くないがリフェは大きな問題はないのでやってください.ただ満充電での放置は☓)
② バランス端子が細く死にやすい
③ 衝撃などに弱い
④ 短絡させると煙が出る(モータ直結させるのは辞めてください
最後に
情けない先輩ですが温かい目で見てやってください。
